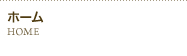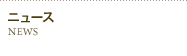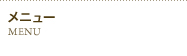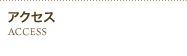ホーム > ニュース
- オーガニックコラム
- 2023年12月12日
健康長寿食を目指して
最近、現代型栄養失調という言葉を聞くようになりました。
以前から現在の野菜は栄養価が低くなっていると言われていますが
ところがこの野菜、
- オーガニックコラム
- 2019年11月01日
やってきた食糧危機
- オーガニックコラム
- 2019年10月15日
カブトムシは従業員?
有機農法には堆肥は重要な資材です。4年前に樹木を選定した枝のチップを頂きました。180cm×360cmの囲いの中の約半分くらいの中に、150cmほどの高さまで米糠150㎏を混ぜ合わせて積み上げました。その後カブトムシが大量に発生しました。切り返しの時スコップですくうと10匹くらいいました。全体では1000匹を超すのではないかと思うほどの数です。毎年野菜の苗を移植したとき株元に少量ずつ置いていますが、今年はその堆肥には樹木の固形物はなくなり、よく見るとカブトムシが食べて糞になったものでした。カブトムシが木くずをかみ砕いて食べてその結果素晴らしい堆肥になっていたのです。
9月中頃メスのカブトムシが数匹来ていましたので産卵していたのかもしれません。昨年頂いた新しい木くずを運び込んで用意をしました。カブトムシに堆肥を作るように指示したことはありませんが、毎年大量のカブトムシが堆肥の製造をしてくれています。しかも無給です。人間が作るとなると茸類の菌床におがくずを使用しますが、茸の栽培が終わった廃オガ屑でしょう。カブトムシの場合、体内を通して出てきたものでオガ屑くらいの大きさになっていて、すぐ土に混ぜても何の害もありませんし使いやすい肥料になっています。
自然には害をなす虫もいればカブトムシのように肥料つくりに励んでくれている虫もいます。私から見れば実によく働く、堆肥製造部門の従業員のような存在です。ただ今年は猪のために大量のカブトムシが食べられ犠牲になりました。今はワイヤーメッシュで入り口を塞ぎ、猪が侵入しないように防ぎました。今年産卵したのでまたカブトムシが木くずを食べて、元気に育ってくれればと願っているところです。
槇本清武
- オーガニックコラム
- 2017年02月17日
健康法はいろいろあるけれど
- オーガニックコラム
- 2016年05月10日